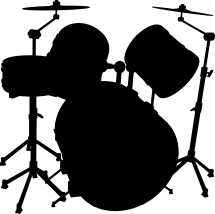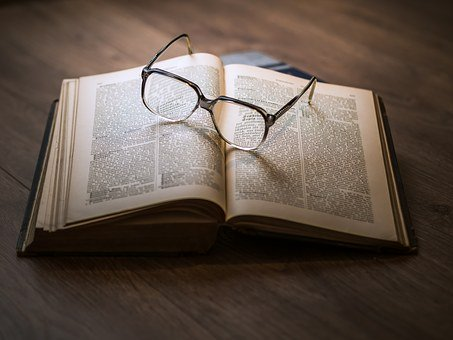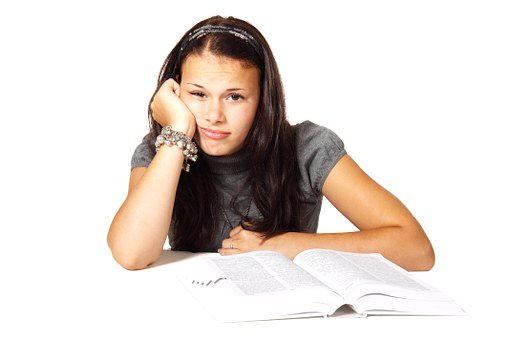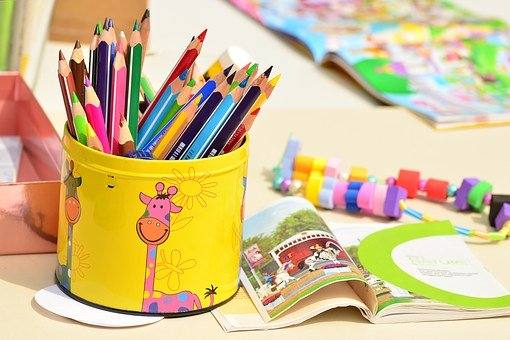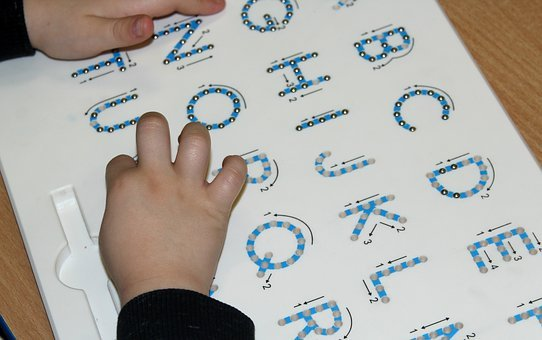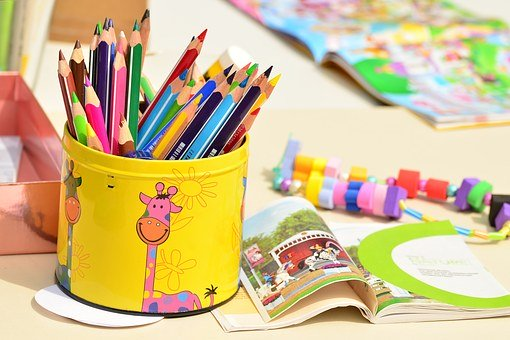子ども向けのウクレレを探していますか?

子どもにウクレレを習わせたい、または触れさせてみたいと考えている場合、子ども用のウクレレが欲しいと思いますよね。
ウクレレは、子どもにもぴったりなうえ、パパやママにもメリットがたくさんある楽器です。
- 他の楽器に比べて安価
- 小さい楽器のため子どもの身体に負担がかからない
- 自宅に楽器を置くスペースを必要としない
- 音が小さいためいつでも演奏可能
子どもが興味を持った、またはパパやママが子どもに楽器を始めてほしいと思っているときに、始めやすい楽器。
そんなウクレレですが、もともと小さいですし、子供用のものも販売されています。せっかく始めるのであれば、子どものサイズに合わせて購入するのがおすすめです。
次では、子ども向けのウクレレを選ぶ場合のポイントをご紹介します。
子ども向けのウクレレを選ぶ場合の注意点

せっかく子どもにウクレレを購入するのであれば、意欲的に取り組んでもらいたいと思いますよね。そこで、ウクレレを選ぶ際に注意したいポイントを3つご紹介します。
子どもが気に入り、意欲的にウクレレに取り組んでもらえるものを選びましょう。
ちなみに、ウクレレにはサイズがあります。「ソプラノサイズ」「コンサートサイズ」「テナーサイズ」「バリトンサイズ」がありますが、初心者や子どもはまず一般的な「ソプラノサイズ」を選んだ方がいいと思っておきましょう。
もちろん、子供用として販売されているウクレレもたくさんありますよ。
①素材を確認しよう

ウクレレと一言でいっても、サイズや素材など様々なタイプのものが販売されています。ウクレレに使用される素材は何種類もあり、見た目も音色も違ってきます。
ウクレレといえば、「ハワイアンコア」や「マホガニー」が主流ですが、その他にも「マンゴー」「メイプル」「スプルース」などがあります。
子ども用に購入するのであれば、マホガニーがおすすめです。
1919年創業のウクレレ専門店であるKIWAYAでは、マホガニーを
高音域や音抜けの良さでも安定感のある材です。
1919年創業のウクレレ専門店KIWAYA
https://www.kiwayasbest.com/html/page6.html#beginner-WOOD
と紹介しています。さらに、マホガニーは丈夫な素材です。楽器の扱いに慣れていない子どもに持たせる素材としてもぴったりです。
これだけ魅力ある素材にも関わらず、マホガニーを使用している楽器は安価で購入することができます。どこまでウクレレを続けてくれるかわからないけれど、マイ楽器を持たせたいという場合にもおすすめできる素材ですよ。
その他の特殊な素材を使用したウクレレは、高価なものが多いですし、初心者や子どもには向きません。高額だからいいというわけではないため、注意しましょう。ぜひ、購入時はウクレレの素材も確認するようにしてください。
②安価すぎるものには要注意!

ウクレレは低価格で購入できるメリットがあると紹介していますが、安価すぎるものを選ぶのは危険です。
安すぎるものは、おもちゃと変わりません。長く使うこともできないでしょう。
購入しやすいですが、音が狂いやすい点も難点。音楽的感覚を身につけられる時期に、狂った音で演奏させたくはないですよね。
せっかく楽器に触れさせるのであれば、本物を選びましょう。ウクレレは楽器自体それほど高額なものではないため、安価すぎるおもちゃのようなウクレレを持たせるのはやめておきましょう。
③愛着が持てるものを選ぶ

ウクレレはそれぞれ形やデザインが違います。せっかくなら、子どもが気に入る、愛着が持てるものを選ばせてあげるのもいいでしょう。
子どもが気に入ったデザインのものを選べば、よりウクレレに愛着が持てますし、意欲的に挑戦してくれる可能性あるでしょう。
カラフルなウクレレ、デザインが可愛らしいウクレレなど様々なものが販売されているので、ぜひ子どもと一緒に買いに出かけてください。
【子ども向け】購入すべきおすすめのウクレレ5選

続いて、子どもに向いているおすすめのウクレレを5つご紹介します。デザインや形もいろいろなので、子どもが気に入るものがあるかどうか、価格とあわせてチェックしてみてください。
①MAHALO ソプラノ UKULELE アートシリーズ ハート MA1 HE ブラック

3,691円
何より可愛らしいデザインが魅力的なウクレレです。女の子なら、一度手に取ってみたくなるのではないでしょうか。もちろん魅力なのは、見た目だけではありません。
お試しでウクレレに挑戦したいと思っている方でも、手が出やすい価格もポイント!有名メーカーのウクレレというのも、安心要素ですね。
②MAHALO スマイル ウクレレ 初心者用セット ソフトケース クリップチューナー 教則DVD U

4,063円
続いてもMAHALOのウクレレを紹介します。可愛らしい顔が特徴的なカラフルなウクレレで、子どもにもぴったり。
さらに、この商品はウクレレだけでなく、ソフトケースやチューナーなどウクレレを始めるうえで必要なアイテムも揃っていますよ。
③aNueNue U900カラーウクレレ[ピンク] [くまのクレレ]6点フルセット

21,700円
他のウクレレと比べると少し高額ではありますが、こちらのウクレレも子どもにぴったりで人気があります。とっても可愛らしい見た目もいいですね。
もちろんウクレレとしてもクオリティーが高く、他のウクレレに比べると弦が押さえやすいのも魅力です。
④Aostinオースティン UMI-1 ソプラノウクレレ マホガニー材

5,990円
シンプルかつ、すぐに始められるウクレレセットが欲しいという場合におすすめなのが、こちらのウクレレです。マホガニー素材のウクレレで、子どもでも扱いやすいでしょう。
さらに、すぐに始められるようにチューナーや教則本も付いています。それでいて5,990円という価格も魅力です。
⑤Enya EUP-X1 人気のソプラノパイナップルウクレレ

9,000円
よくみるウクレレの形ではなく、パイナップル型のウクレレです。その見た目のキュートさも魅力的です。
こちらの商品も、ケースやチューナーなど様々なアイテムとセットになっています。スターターセットとしておすすめの商品ですよ。
ウクレレは子供が小さいうちから始めよう!まずは無料体験から

お子さんをウクレレ教室に通わせてみませんか?
早いうちから、楽器を触り音を出す習慣をつけることで、感性を磨いていくことができます。3歳からでも全然早くなく、早ければ早いほど良いのです。
今なら、EYS音楽教室で無料レッスン体験を実施中!
まずは無料で、お試ししてみてはいかがでしょうか。

【子ども向け】おすすめのウクレレ練習曲3選

子ども向けのおすすめウクレレ練習曲も3曲ご紹介します。子どもと練習するのであれば、コードが少ない曲、子どもが知っていて楽しく練習できる曲を選ぶのがポイント!
①線路は続くよどこまでも
子どもだけでなく、パパやママも知っていて一緒に練習したり歌ったりできる「線路は続くよどこまでも」は、コードが3つしか登場しないため、子どもでも練習できる曲です。CとFとG7のみが登場する曲なので、練習してみてはいかがでしょうか。
② むすんでひらいて
こちらもみんながよく知る曲、「むすんでひらいて」です。この曲も3つのコードだけが登場する曲なので、子どもでも練習しやすいです。パパやママと一緒に歌いながら練習してみてください。
③幸せなら手をたたこう
「幸せなら手をたたこう」は4つのコードが登場する曲です。家族みんなで楽しく歌いながら練習できる曲でもあるので、チャレンジしてみてもいいでしょう。
子どもにウクレレを習わせるならEYS音楽教室へ

子どもと自宅でウクレレを練習していても、限界がありますよね。きちんと教室に通うことで、より上達するのかもしれませんし、もっとたくさんのことを知れる可能性もあります。
しかし、ウクレレを教えてくれる音楽教室を探すのも大変でしょう。
そこで、ここで紹介したいのがEYS音楽教室です。EYS音楽教室は、関東に22のスタジオを持っているため、通いやすい教室を選択することが可能です。
さらに、ウクレレコースは幼児から通うことが可能なので、ウクレレに興味を持った段階でレッスンを受けることもできます。
その他にもパパやママが嬉しい魅力があるため、ご紹介しますね。
- 楽器プレゼントがある
- レッスンのやり直しが可能
- 補講が無料
- イベントが豊富
なんとEYS音楽教室は、条件さえクリアすれば楽器をプレゼントしてもらえます。ウクレレコースの場合、マホガニーを使用したウクレレでをプレゼントしてもらえるため、本格的なウクレレを最初から手にすることが可能です。
また、レッスンに満足できなかった場合は、他の先生でレッスンをやり直してもらえます。これなら子どもとの相性がいい先生を見つけることも可能。となると、子どもが長く通い続けてくれる可能性も高くなるでしょう。
さらに、急なお休みでも補講をしてもらうことができます。この制度があるからこそ、月謝を無駄にすることがないのです!
そして、子どもにとって嬉しいのがイベントが豊富な点でしょう。ハロウィンやクリスマスなどに、他の生徒と関わり合いが持てるので、お友達もできますし、いいライバルに出会えるかもしれません。
これだけ魅力があるEYS音楽教室は、無料で体験レッスンを受けることができます。ぜひ教室や先生の雰囲気を見に、一度体験レッスンへ出かけてみてください。
最後に

子どもにおすすめのウクレレや、ウクレレの練習曲をご紹介してきました。子どもでも始めやすいメリットがたくさんある楽器がウクレレです。
子どもが興味を持ったら、ぜひやらせてあげましょう。パパやママと一緒に歌いながら練習すれば、楽しい時間が過ごせるはずですよ。
もちろん自宅での練習に限界を感じたら、音楽教室に通ってレベルアップを目指すのもいいでしょう。その際は、EYS音楽教室の体験レッスンを受講し、音楽教室とはいったいどんなところなのか、見に行ってみてください。
ウクレレは子供が小さいうちから始めよう!まずは無料体験から

お子さんをウクレレ教室に通わせてみませんか?
早いうちから、楽器を触り音を出す習慣をつけることで、感性を磨いていくことができます。3歳からでも全然早くなく、早ければ早いほど良いのです。
今なら、EYS音楽教室で無料レッスン体験を実施中!
まずは無料で、お試ししてみてはいかがでしょうか。